「薬剤師への道標」 (第3回)
9.日本における西洋医薬品の歩み
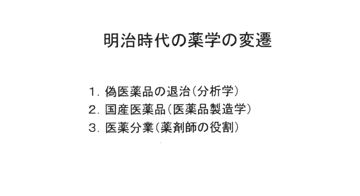
そこで日本はどうしたかというと、江戸時代まではまったくそういう西洋医学は入れなかった。鎖国をしていましたから、入れていないんですね。ところが明治になって鎖国が解ける、黒船が来た。黒船は何を持ってきたかというと、かなりの医薬品です。鉄砲も持ってきましたけれども、西洋医薬品を持ってきた。その前にシーボルトが長崎に来ていますから、もう漢方医学に取って代わって西洋医学というのが怒濤のごとく幕末に入ってきました。そして、明治元年には、もう1万人ぐらいの西洋医が日本ではできていた。その時に、薬剤師はゼロです。いくら西洋医がいても、西洋の医学をやるためには、薬がなかったらできないわけです。手術をするとか、いろいろなことは持ってきますけれども、薬がない。日本はつくっていないわけですから。
その後黒船が持ってきたのは、密輸も含めて西洋医薬品です。たくさん持ち込んできました。ところが日本へ持ってきたのは、ほとんどすべて西洋では使えなくなったような悪い品物。日本も東南アジアに一時、日本では禁止したDDTとかBHCなんていうものをずいぶん輸出していた時代があります。酷いなと思いました。発展途上国には、先進国はいつもそういうことをやるんですね。
それで、西洋医学ではアスピリンを使う。アスピリンはまだなかったぐらいの時で、アスピリンを使いたい。ところがアスピリンというのは、日本人は見たこともないものですから、誰が見ても分からない。そうすると、「これはアスピリンです」と言われたら、アスピリンだと信じるしかない。西洋医学を学んだお医者さんが、「アスピリンを使いましょう」と言ったら、それを使うしかないわけで、明治の初年に、江戸から東京になりますが、その東京で、人が死んでしまうようなものすごい医薬品の被害が起こるんですね。ところが、まだ日本では薬学というものがありませんで、特に分析学というのがない。何とかして偽医薬品、あるいは悪い質の医薬品を何とかしなければならないということで、明治政府は悩むわけです。そこで、薬学部をつくって、薬学の研究者をつくらないと、とてもじゃないがこれは対処できないという話になって、明治4年に、いまの東大の中に薬学部をつくるわけですね。そして、最初に分析学をやる。早く分析学をつくり上げて、分析をするところをつくらないと、日本国中が偽ものだらけになる。効かない医薬品ならばいいけれども、他のものが混じっているというのでは困ってしまうということで、そのために、薬学というのは、まず分析学を導入したというのが明治の始めにあります。
けれども、こういうことばかりやっていてもしょうがない。だって向こうから入ってくるものをいくら見張りをしていたって、いたちごっこなわけです。早く国産の医薬品をつくらなければならない。日本に製薬会社をつくり、国がそれを統一して良い医薬品をっくらなければならない。医薬品製造学というものを早く教えてもらって……特にドイツからですが、日本でそういうものをつくろうと。そして明治の中期に、大日本製薬という、国が国家管理するような製薬会社ができます。いまでもありますが、マルP(株)という、これはもう独立して国から離れていますが、そういう国産の医薬品をつくる、日本薬局法をつくろうという動きがある。
そして、そういうことが終わった段階で、今度は流通の中で毒殺を防止しなければならない。お医者さんに全部診断権、処方権、調剤権を預けておくことは、ものすごく危険である。西洋ではもうそういうことだったから、早く薬剤師をたくさんつくって医薬分業の受け皿にしなければならないという動きが出てきます。実は、この処方せんというのは証拠物件になるんですね。薬局では処方せんは3年間取っておかなければならない。裁判が起ったらこれが出ていって、お医者さんが間違えたのか、薬剤師が間違えたのか、あるいは意図的にそういうことをやったのか、これは大変なことになりますから、処方せんというのは完全な証拠物件で、患者のものなんです。それを薬局は預かって3年間保管をするというシステムですから、患者の安全性というのを、一連のその流れの中で処方せんだけを抜き上げてしまうんですね。医師は調剤ができないという法律を日本国も持ってきた。しかし、残念ながらそれから100年間、薬剤師の数が少ないという理由でできなかったのですが、いまそれがやっと芽を出してきたんですね。
10.自己と他己
「自己と他己」という話をしょうと思います(スライド)。「他己」という表現はあまり聞いたことがないかもしれませんが、自己というのは、自らのおのれ。他己というのは、他のおのれと書きます。これは、仏教では有名な話のひとつで、私の大好きな話です。マツリカーという当時のインドの皇太子妃殿下と皇太子です。いまの雅子妃のごとく2人は恋愛をして結ばれるわけですが、インドで月の綺麗な晩にバルコニーに出て、この2人が話をします。「この世でいちばん愛している者は誰か」と、この王子様はお妃に聞くんですね。ロマンチックな夜に、おまえはこの世で誰をいちばん愛しているかと。これはもう答えは予想されるんですね。「あなただ」と言ってもらいたくて聞いていることは見え見えなわけです。ところがこのマツリカーというお妃は、とても利口な、哲学的で感性のいいお姫様でしたから、ジーつと考えた末に、何と答えたと思いますか。「私自身です」と答えているんですね。「あなたではありません、私がいちばんこの世で愛しているのは私です」、エゴイズムだと思いますか。
それでこの王子様は怒るんですね。カンカンになって怒る。「自分自身をこの世でいちばん愛しているとは何事だ」という話ですよね。ところが、この王女様は非常に冷静ですから、「あなたもゆっくり考えてください。恋愛結婚でアツアツの場合は『あなたです』なんていうことを言っているけれども、一生を通して本当に考えていったら、あなただって自分がいちばん愛おしいでしょう。3日、4日の問題じゃない。本当に大事なのは、私自身ではないですか」という答え方をするのですが、どうですか、感想は。
「その通りかもしれない」(学生)
その通りかもしれないという共感が出てきましたね。とても面白い。どうですか。
「その通りだと思います」(学生)
共感が多いですね。この王子様もそう言われて、よおく考えてみた。時間をおいて冷静に。そして、「おまえの言うのが正しいかもしれない。私も、私自身がいちばん愛おしくて、いちばん愛している」というふうな確信が出てくる。けれども、「これはおかしい」と。そんなことを考えていたら、国が治まらなくなってしまうわけです。みんな私自身がいちばん愛おしいと考えたら、エゴイズムが氾濫して、人類社会とか王様の国というものはなくなってしまう可能性がある。誰かに「これでよろしいか」と、聞かなくてはいけない。ちょうど近くに祇園精舎か何かそういうところがありまして、お釈迦様が来られていた。お釈迦様は絶大な信用を得ているわけですから、お釈迦様のところに2人で行って、これでいいかどうか聞いてみようというので、2人で聞きに行くわけです。「かくかくしかじかで、こうなりました」と。お経に書いてあるんですね。お釈迦様は何と言ったと思いますか。「それは正しい。その通りだ」と。あなた方2人の話はとても正しい。「正しいけれど、しかし……」と、必ず「しかし」がつくんですね。ここからが問題なんです。ここから先が感性と哲学の世界です。決め手というのは、常にそこから先。あなた方が学ぶのも、ここから先ですよ。そこまでは誰でも行く。そこから先を学ぶか学ばないかによって、自分の人生が豊かになるか、薬剤師としてのあなた方の人生が豊かになるかが決まってくるということです。心を研ぎ澄ましてこの問題を耳の中に入れなければいけない。
そこから先。「しかし、あなた方が言うように、すべての人は世界一尊いと自分では思っている。となれば、あなたも、あなたも世界一尊い」と。ここにいるすべては世界一尊いものの集まりなんですね。ここに犬が一匹入ってきても、それは世界一尊い犬なんだと犬は思っているに違いない。猫が入ってきても、私は世界一尊い猫と思っていると言うに違いない。客観的に見ても、そういう世界一尊い人たちの集まりなのだから、すべての人は、お互いにそういうつもりで付き合いましょうというのが結論なんです。世界一尊いんですよ、犬も猫も。あなたも私も世界一尊い。誰も否定していない。相手も世界一尊いということを認めていったら、この世はどうなるかという問題です。殺すとか、殺さないとか、猫一匹でも、犬一匹でも、そうでしょう。相手は世界一尊い人なんです。自分も尊いということを認めたうえで、相手も尊いということを認める。まさに医療という世界はそうなんですね。患者さん、お医者さん、薬剤師、看護婦、みんなそこにいる人たちは世界一尊い、患者さんも尊い、そういう中で行われるのが医療の原点であるということを教えているわけですね。だから、お釈迦様がよく言う「しかし……」というそこから始まる話こそ、本当に逆転の発想でありながら、真理というものに近づいていく。そういう話がいっぱいあるんですね。
